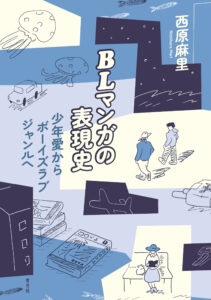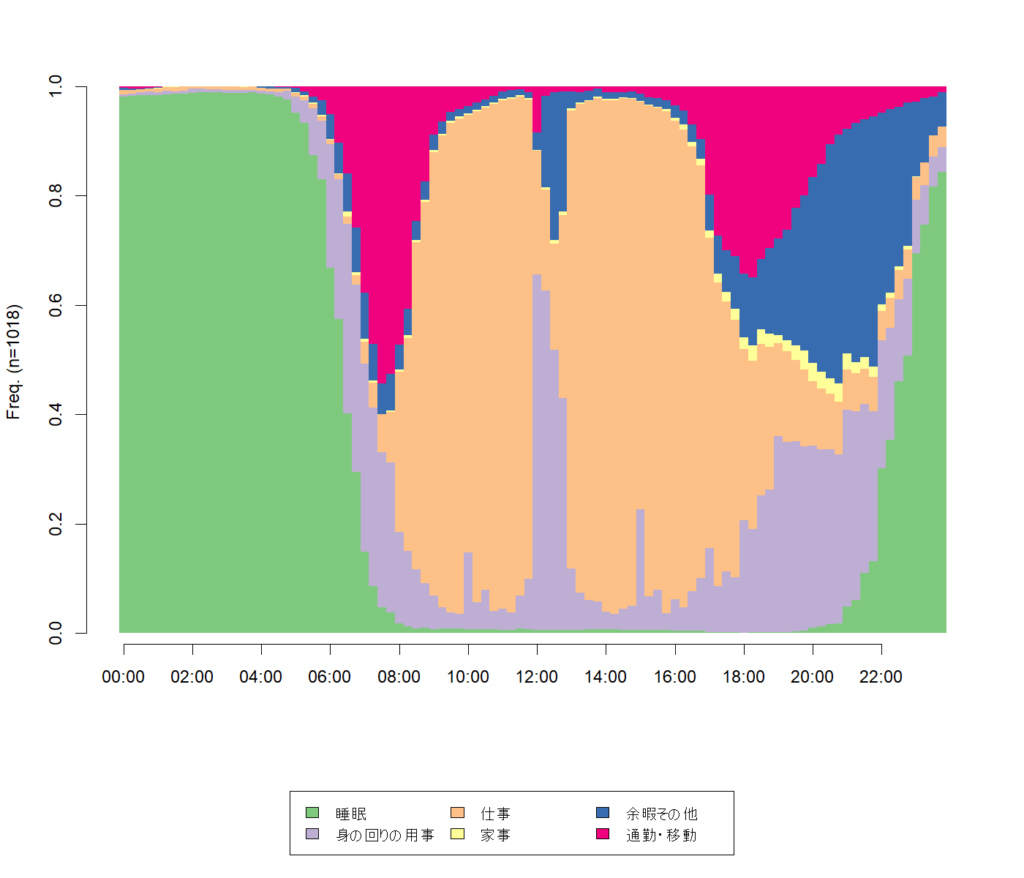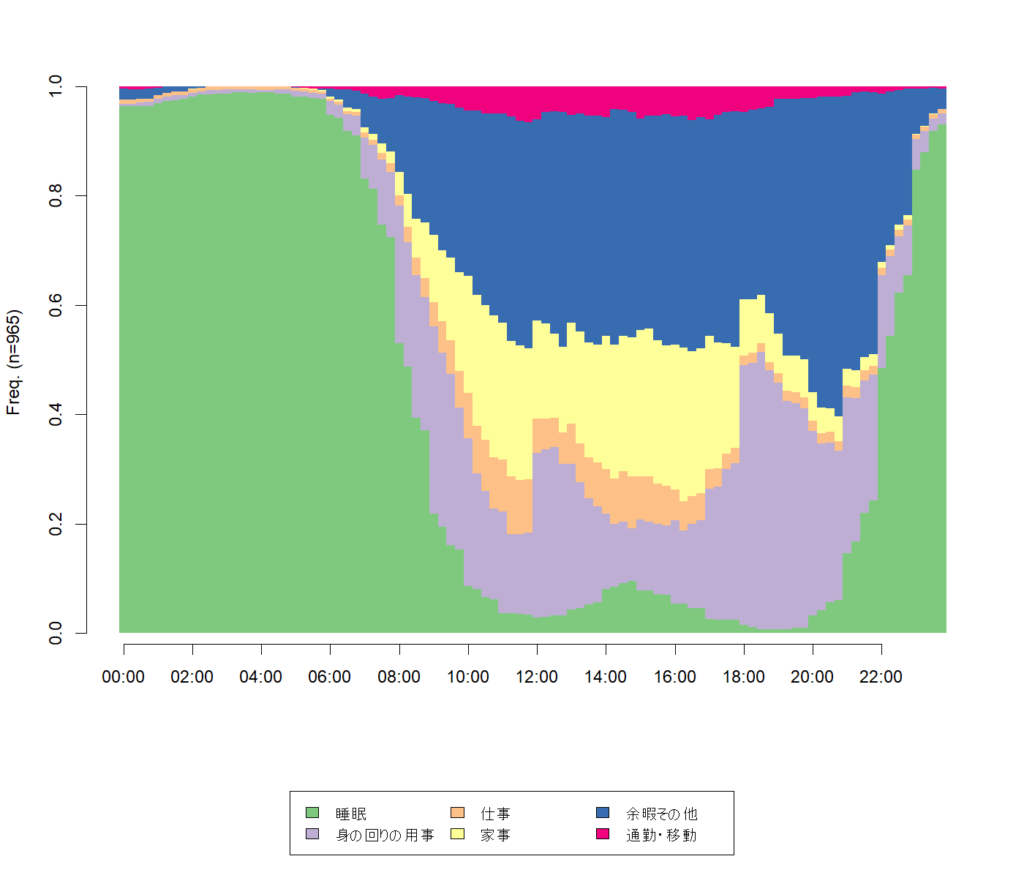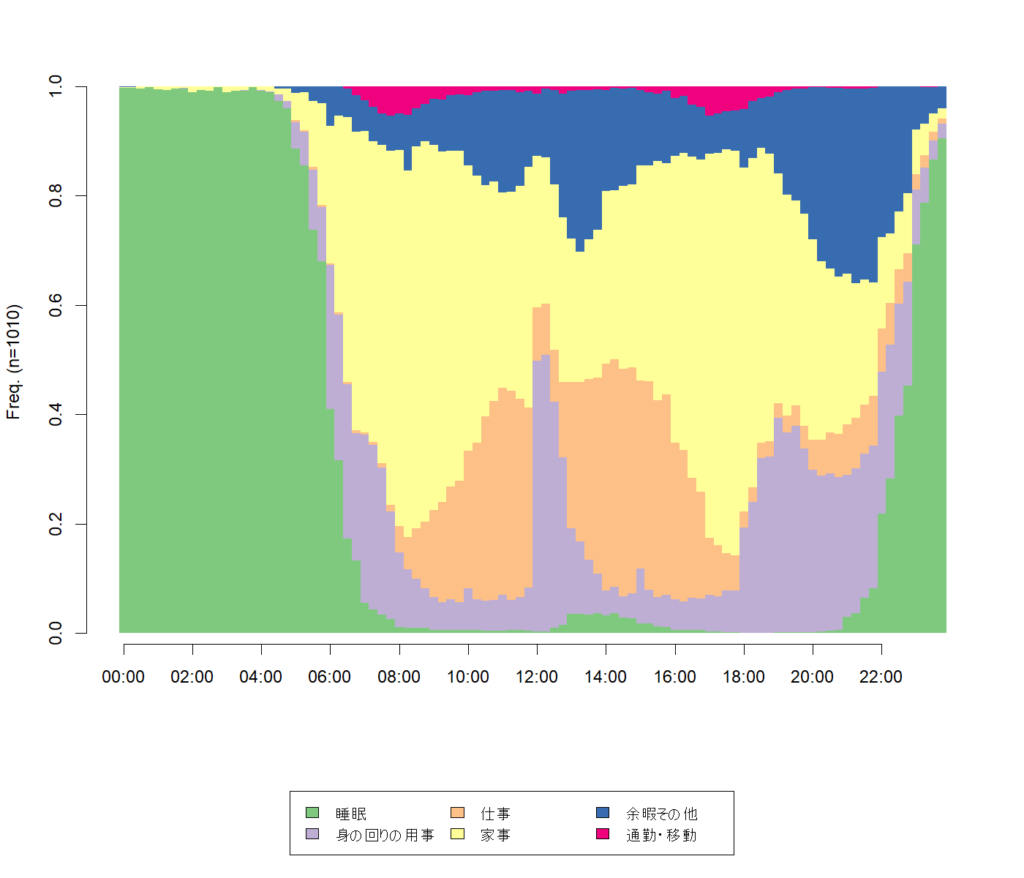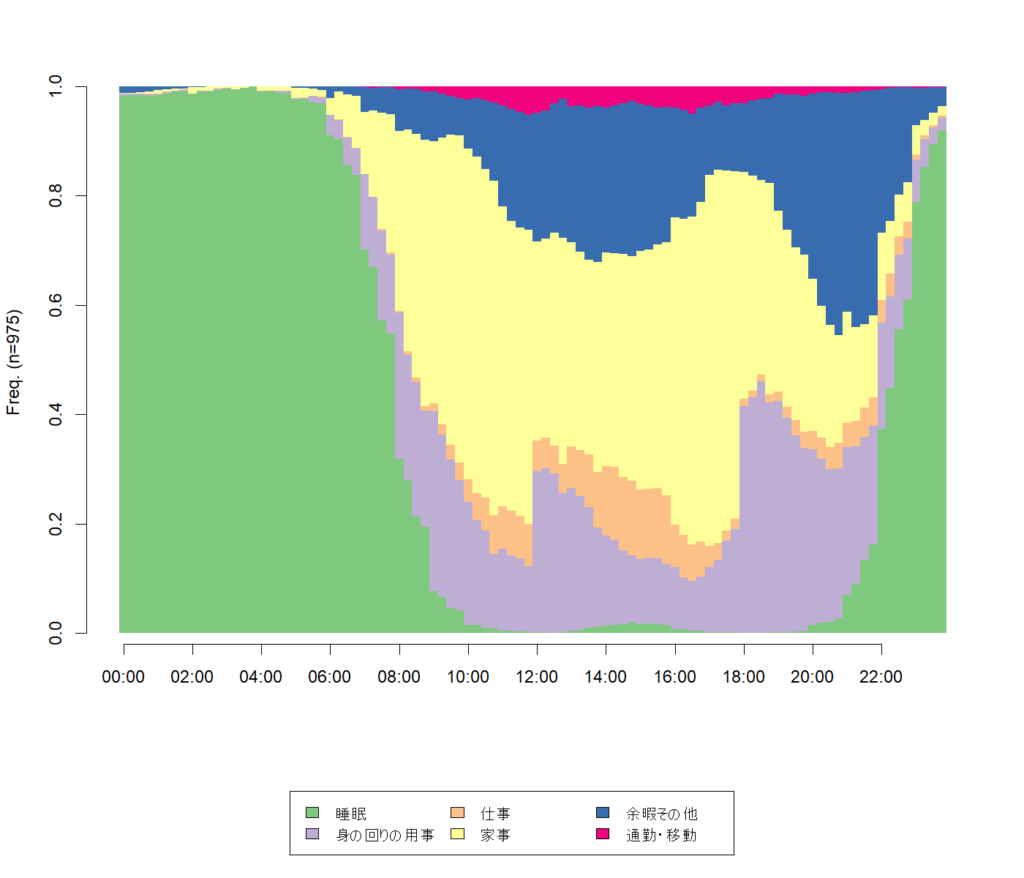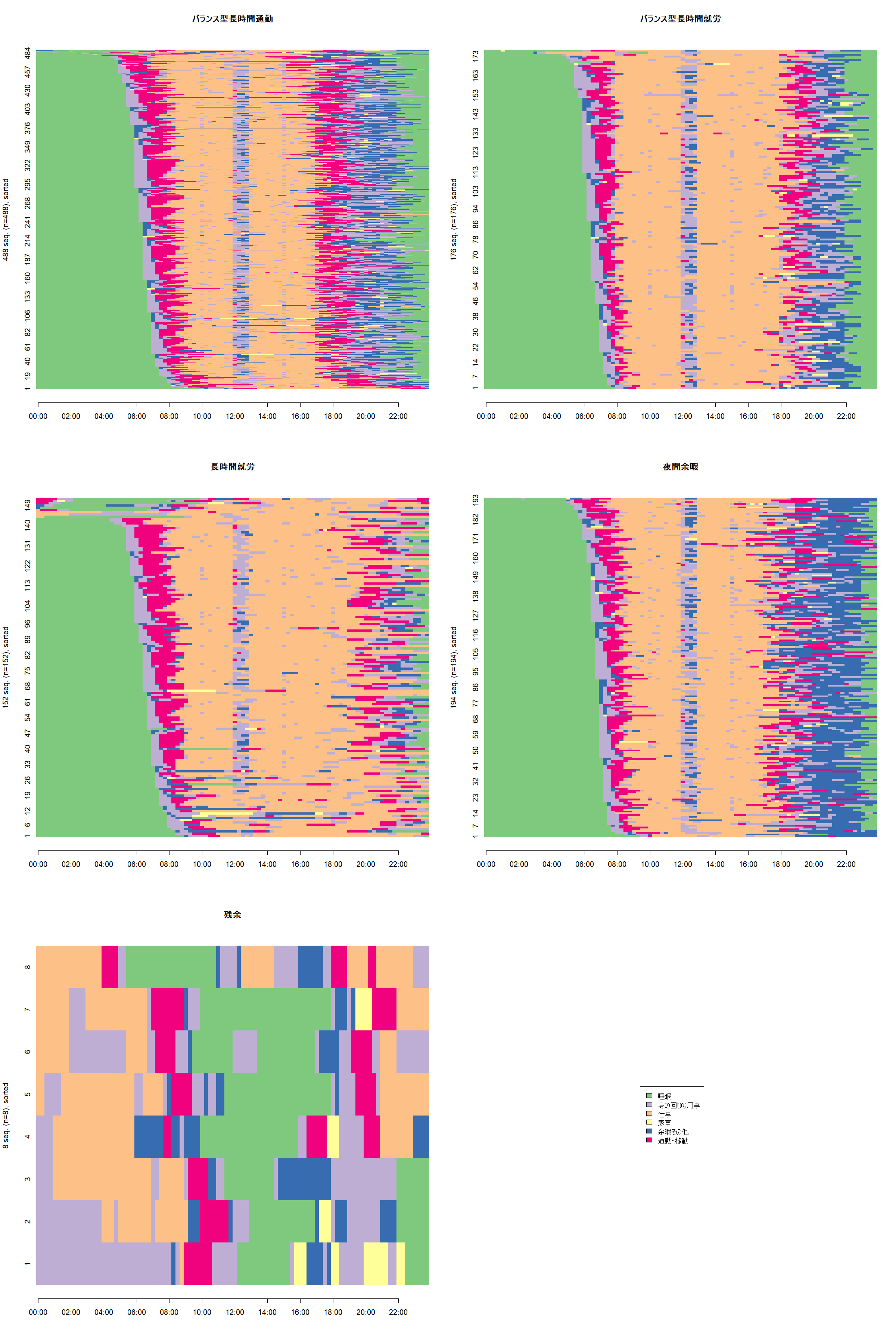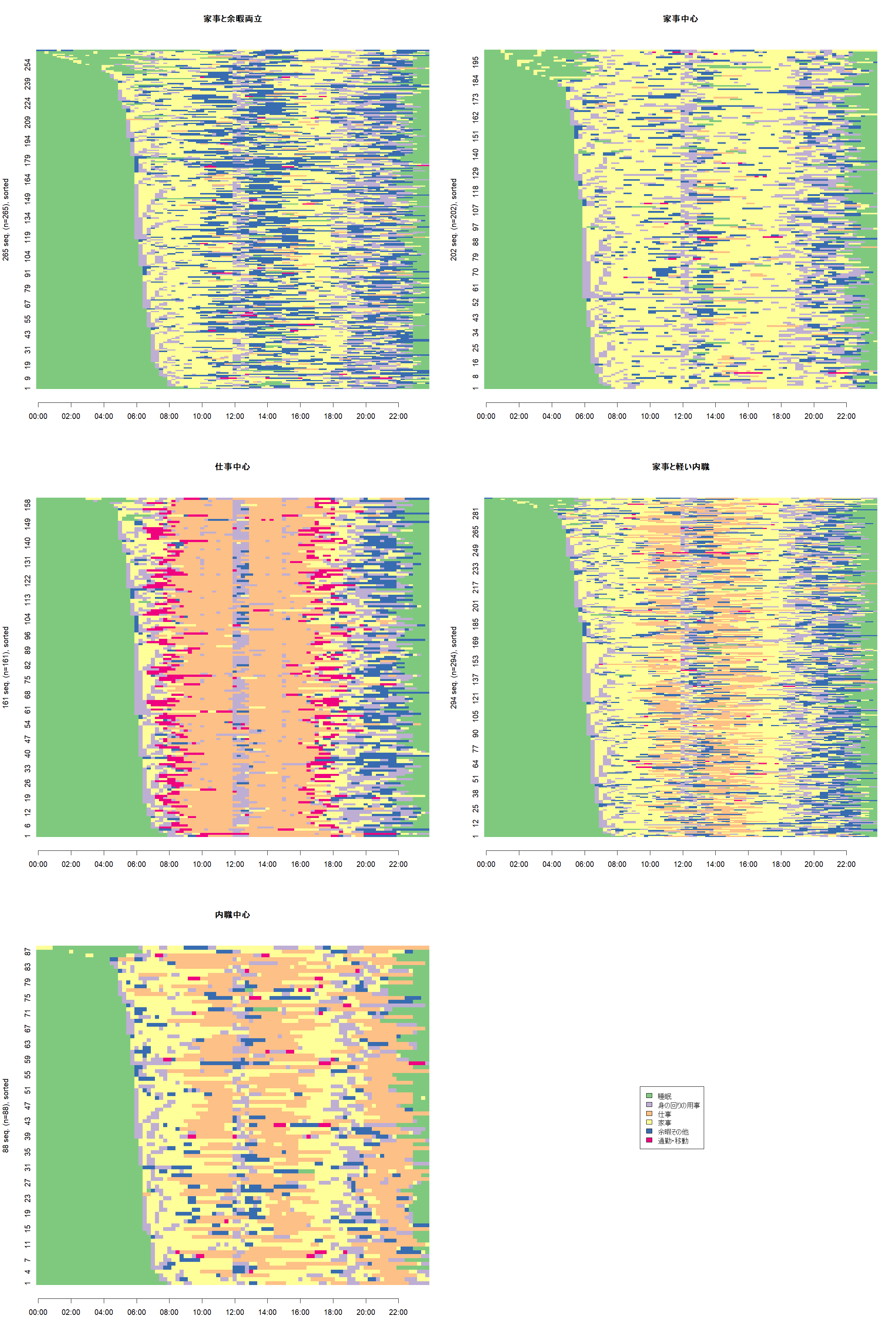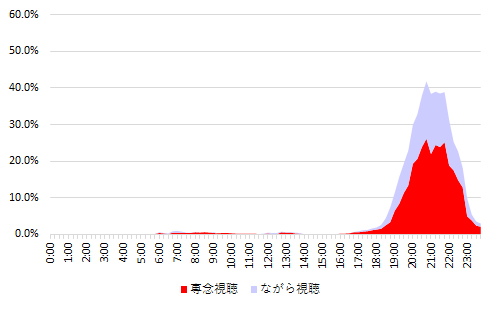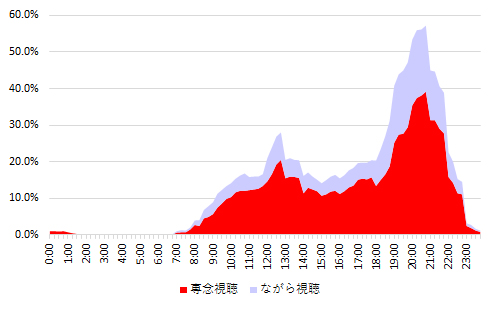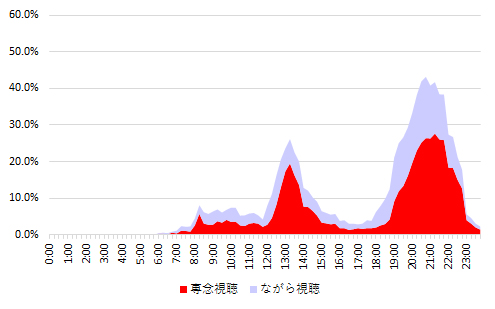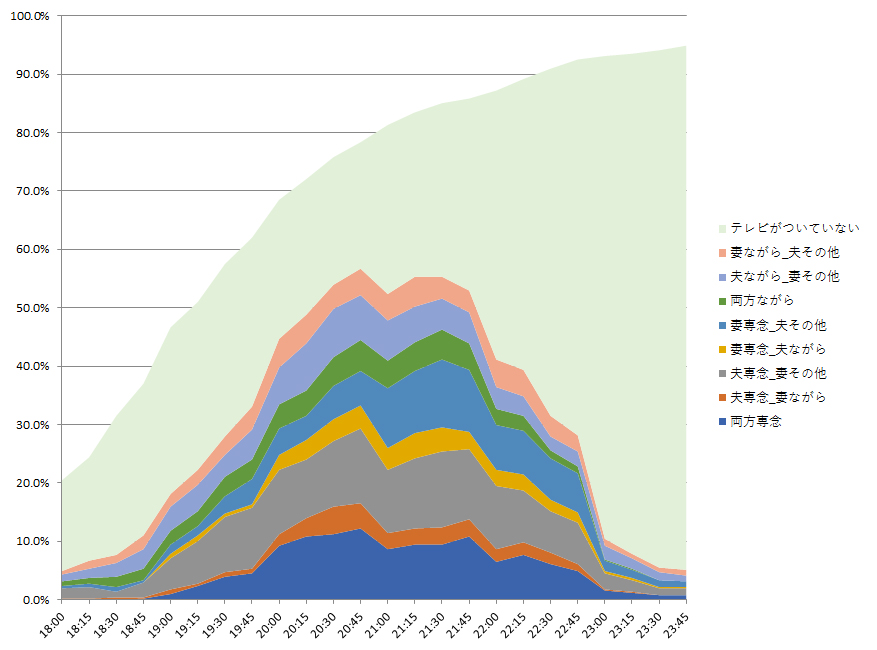『おぞましさと戯れる少女たち』刊行記念トークイベント
少女表象からアートとフェミニズムを問う
山田萌果×吉良智子×横田祐美子

■ 趣旨 ■
今月2月、山田萌果さんの著書『おぞましさと戯れる少女たち』を刊行しました。本書は、フェミニズム美学の視点から、現代日本美術のなかの少女を描く作品を読み解き、作家が仮託したものや作品の芸術的な価値を明らかにしています。
本書の刊行を記念し、近代日本美術史が専門の吉良智子さん、現代フランス哲学が専門の横田祐美子さんのお二人を招きして、トークイベントを実施します。
近年の少女表象の特徴や美術史での位置づけ、おぞましい少女を描く作品がもつ引力のありか、フェミニズム美学の可能性などを縦横に語り合っていただきます。
また、吉良さんと横田さんは3月に『アートとハラスメント』(竹田恵子さん、長倉友紀子さんとの4人の共著、岩波書店)を出版します。女性作家とアートシーンの関係など、作品読解にとどまらない対話になるかもしれません。
ご興味がある方はぜひご参加ください!
■ 日時 ■
日程:2月28日(土)
時間帯:14時30分-16時30分
方法:対面(定員40人)とオンライン
※オンラインはZoomでの配信になります。
※アーカイブ配信もあります。オンラインチケットを購入してくださった方に、後日、動画のURLをお送りします。
■ 場所 ■
場所:ワイム貸会議室高田馬場4階 Room 4C
高田馬場駅から徒歩5分
169-0075 東京都新宿区高田馬場1-29-9
https://waim-group.co.jp/space/takadanobaba/access.html
■ 参加 ■
※参加希望の方は、以下のサイトで「チケット」をご購入ください。
対面での参加チケット:1,100円(税込み)
https://seikyusha.stores.jp/items/698d671b8feb784147bdc4a7
オンラインでの参加チケット:1,100円(税込み)
https://seikyusha.stores.jp/items/698d66938feb783cb2bdc462
書籍購入(書籍は郵送)+参加チケット:
【会場参加チケット+書籍】:4,840円(税込み/送料無料)
https://seikyusha.stores.jp/items/698d688fd87efe544688b8d1
【オンライン参加チケット+書籍】:4,840円(税込み/送料無料)
https://seikyusha.stores.jp/items/698d681ad87efe4fbf88b8f8
■ 登壇者のプロフィル ■
山田萌果(やまだ もえか)
北海学園大学・北翔大学非常勤講師。専攻はフェミニズム美学、少女論。論文に「嶽本野ばらの描く「乙女」の主体性――澁澤龍彦「少女コレクション序説」との関連性をめぐって」(「ユリイカ」2024年5月号)など。
吉良智子(きら ともこ)
日本女子大学学術研究員、東洋英和女学院大学ほか非常勤講師。専攻は近代日本美術史、ジェンダー史。著書に『女性画家たちと戦争』(平凡社)など。
横田祐美子(よこた ゆみこ)
横浜美術大学美術学部助教。専攻は現代フランス哲学。著書に『脱ぎ去りの思考――バタイユにおける思考のエロティシズム』(人文書院)など。
■ 主催・問い合わせ ■
株式会社青弓社
矢野未知生(青弓社)
mail[at]seikyusha.co.jp